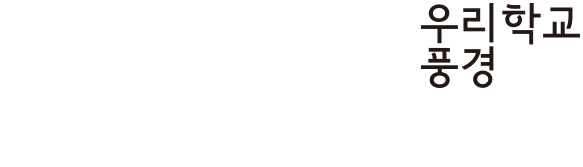「対話」の積み重ねが橋を…。朝大と武蔵美の合同美術展
スポンサードリンク
「塀を取り払う」という言葉から連想するのは「和解」「親睦」「統一」…。「南北朝鮮間の分断の壁(塀)を崩そう」「在日朝鮮人と日本人の間の塀を取り除こう」、それは私たちの望みでもあった。しかし「武蔵美×朝鮮大 突然目の前がひらけて」展(11・13~21)では、両大学を隔てる塀を崩すのではなく、あえて橋を架けた。
始まりは二〇一一年、武蔵美の灰原千晶さんが朝大の男子寮(八号館)の横のアトリエで作品を作りながら、塀の向こうから聞こえてくる声を自覚したことだった。「声が聞こえることを自覚したのは、震災の後でした。声が聞こえて向こうにはどんな人がいるんだろうと思った。話しかけてもらうきっかけになれば良いやと思って、物理的に渡るための橋じゃなくて完成のない構造体『渡れるかも知れない橋』を作ったんです。そしたら、本当に運よく話しかけてくれて、『何しているの?』とか。雨が降ってきたときは『傘持っているの?』とか」。(インターネットサイト「70seeds-戦後七〇年の『知らなかった』と出会う」)その後、彼女が所属する同大の袴田(京太朗:油絵学科教授)ゼミと朝大美術部の交流が始まった。
翌年四月「同じ作り手としてなぜ作るのか?」というテーマで合同展を開催した。ところがこれが終わると、次にどうするのかが見えなくなったという。「『在日』という要素を無視できなくて、お互いの歴史の教科書を交換したりとかしたんです。そういった、政治的な問題や歴史問題に踏み入ってきたあたりで、だいぶ行き詰まっちゃったんですよね。道が塞がっちゃったように感じました」(李晶玉、「70seeds」)「今回は『対話』がテーマなんですが、二〇一二年に一回断念したし、今回もいっぱい止まったし、転んだし、いろんなことがありました。だけど、じゃ、この分かり合えない壁とは何だろうな?と考えるようになりましたね」(灰原、「70seeds」)
その一つが、「壁を取り払う」という議論だった。同展のフライヤーに「閉塞する『塀』が時に何かから守る『壁』にもなるように、反面その安心感から脱しなくてはならないと思うこともある」という朝大・鄭梨愛さんの文がある。「塀を取るという案で話が進みそうなときに、書いた文章なんです。私は、塀を取るという案に対してすごく拒絶反応があって、塀は、壁はむしろあってほしいし、それはいじっちゃダメだと思ったので、それをとりあえず文章にまとめたんです」。
一方、武蔵美の灰原さんは「わたしは、塀を取る案が出たときに、『それでも良いじゃん』と思ったんですよ。川が二本流れていて、間のしきりを取ったら溶け合うじゃないですか。そんな風にしか考えていなかった。…多文化主義とは何か? という講義に参加する機会があって、そこで『同化主義』という言葉が出てきて、ハッとしたんです。今回の企画展を進めていく対話の中で、何度かしている失敗ではあるんですけど、無意識にマジョリティー側の意識を押し付けているんだと自覚しましたね。そういうつもりは無かったのに、同化主義的な考えだったんだなって」。

フライヤーに書かれた「垣根を取り払って話し合うという比喩表現がありますが、実際の塀というものが単に敷地を隔てるものではなく、双方の立場を明確にし、違いをあえて強調するものであるならば、それは取り払ってはいけないものです」という文は、そんな葛藤を経て得た結論なのだろう。
武蔵美の灰原さんは「自分が歴史の地続きの上に立っていることへのリアリティーの無さ、マジョリティー側のバックグラウンドへの意識の希薄さとかは、今回のなかで考えたりしました」(「70seeds」)と述べている。それはマジョリティー側だけの問題ではない。マイノリティーの在日朝鮮人社会においても実は切実な問題だ。今日の朝鮮学校の生徒数の減少はそれを如実に物語っている。
誰かと「対話」することは面倒で、時にはひどく傷つくこともある。しかし相手を理解して近づくためにはそれしか方法がないのだ。立ち止まったり、こけたり、先が見えなくなったりしながら、それでも「対話」を続けていくことの大切さを作品は語りかけていた。時代とともに発展する民族教育を途切らせては行けないと強く思った一日だった。
(金淑子・「記録する会」)34
スポンサードリンク