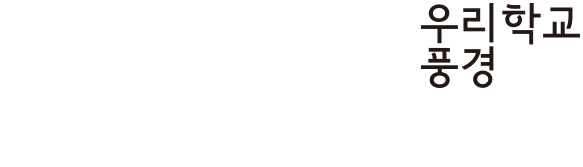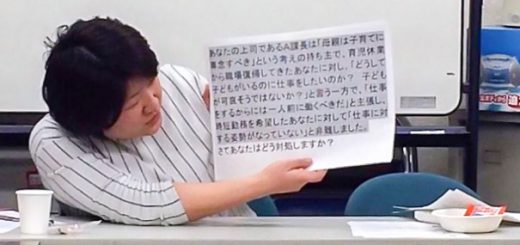祖父母、父母の思い、次世代に伝え、在日同胞社会に根を張って生きる
スポンサードリンク
インタビューを終えて
金淑子・編集部
五月末、休日の李栄祚さんの会社事務所で話を伺った。
幼い頃、夕食のあと、分会や支部に出るアボジの背中を見ながら育ったという李さんの話を聞きながら、昭和の頃の人のつながりを思い出した。当時、親戚は家族のように、ご近所は親戚のように近い存在だった。夕食が住むと誰かの家に集まって世間話をしたり、酒を交わしたり、将棋を指したり…。銀行との取引がかなわなかった同胞たちの間では頼母子講も盛んだった。冠婚葬祭や商売でまとまった資金を用立てるために頼母子講は、同胞社会に欠かせないシステムだったのだ。若い世代も分会に集まってよく飲んでいた。大企業はもちろん中小でも朝鮮人を雇うところはほとんど無かった時代。仕事の紹介や見合い話など様々な生活の情報が行き交った。日本社会の片隅に追いやられた在日朝鮮人たちが、悔しさや歯がゆさを共有し、助け合って気丈に生きる空間がそこにあった。
学校の掲示板に娘の作品が展示されていた。たくさんのお宝にココロ癒された。ハッキョはまさに宝庫です >>>fb2017・6・11一方で、解放以来、脈々と受け継がれた権利獲得運動によって、在日朝鮮人の活動範囲は次第に広まっていった。経済高度成長期、新しい住居を構える同胞たちの多くが、それまでの同胞集住地を離れていった。集住地は本来、行き場のない一世たちが、居住にはそぐわない場所に掘っ立て小屋を建てて住みだしたのが始まりだった。集住地からの移動は、貧しさとの決別を意味した。少しずつではあるが職種も多様化し生活が安定していったが、これと反比例するように、それまで生活に不可欠だった同胞コミュニティーへの依存度は小さくなっていった。
核家族化や余暇の過ごし方の多様化なども進み、同胞コミュニティーが新たなあり方を模索して久しい。朝青当時、英会話教室を開いたり、スキーや海水浴など季節ごとにイベントを組んだり、新聞を出したりと、組織の活性化に苦心した李さんの話からも一九九〇年代当時の様子がうかがえる。そんな中注目すべきは「何しろ一人でも多くの朝青メンバーを集めて未来のハッキョ保護者に、という思いで活動してきました」という彼の一貫した思いだ。朝青卒業後も一口運動や科学雑誌の寄贈など、ハッキョ支援は途切れることなくこつこつと続けられた。
にもかかわらず二〇一〇年のサマーフェスタは「最低だった」。「もうやめよう」と言ったこともあったが、ここからの巻き返しが凄かった。一六〇〇人が集った二〇一六年のハッキョ創立七〇周年の大祝典に至るまでの過程は、「同胞を信じて、思いを伝える」地道な同胞役員たちの努力の積み重ねだった。そしてそれを支えたのは「同胞社会の未来である子どもたちのためにできることはなんでもしよう」という思いだった。李さんの体験は、コミュニティーの中心であるハッキョを守るために、保護者だけではなく、様々な世代の同胞をどれほど多く巻き込んでいくかが、在日朝鮮人コミュニティーの存亡を左右することを示している。「同胞たちにまだ大きな力があるということです。決して小さくない」、李さんの言葉が力強く心に響いた。44
スポンサードリンク