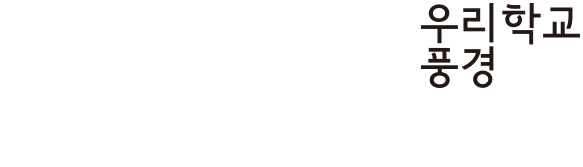仲野先生が育てた芽を枯らさぬように
スポンサードリンク

鳥取大学の学生たちが学美や在日朝鮮人コミュニティと出会った感想を本誌に紹介してくださっていた同大准教授の仲野誠先生が一〇月八日、亡くなられた。
先生にお会いしたのは、昨年一二月、在日朝鮮学生美術展(学美)の東京会場だった。名刺を渡すと、ちょっと驚いたような表情をしていらした。
スポンサードリンク

先生が送ってくださるゼミの学生たちの原稿にはいつも新しい発見があった。学美の作品を見た学生たち、朝鮮学校の運動会に参加した学生たちは、その風景を傍観するのではなく、その中に自分を置いて自分がどうありたいのかを問うていた。彼らの原稿を読みながら「共生」とはこういうことなのかと教えられた。
私が日本の小学校、中学校に通っていた昭和の時代、朝鮮人を擁護する言葉は「日本人も朝鮮人も同じ人間」だった。そう言われるとなんとなく安堵感を感じた。そして「同じ人間」であるために「朝鮮・韓国」と関連するものをできるだけ遠ざけ、打ち消した。
朝鮮大学校で合唱部だった私は、「対外事業」によく駆り出された。当時の交流では言葉通り、内と外がはっきりしていた。内の在日朝鮮人コミュニティ、外の日本人のコミュニティ。「事業」は多分に儀礼的なもので、二つを分かつ壁が崩されることはなかった。
一九九〇年代に冷戦が収束し、それまで大きく二つに束ねられていた運動が多様化した。ショックだったのは、かつて私たちを支持してくれた団体の人たちが、得意の朝鮮語を使って、「アジア女性基金」の受け取りを拒否している、「従軍慰安婦」にされた韓国の被害者の説得に回っているという話を聞いた時だった。私たちは、理解されていたわけではなかったのだ。日本に活動中止を求めに来た被害者の女性たちと、「アジア女性基金」のやり取りは、植民地の女性と宗主国の男性の構図そのものだった。「国が謝罪することはないから、基金を受け取って納めなさい」という彼らに、「二度と同じような被害を受ける女性が出ないようにしなければ」という被害者女性の叫びは届かなかった。
あれから二十年、今、在日朝鮮人と日本人のあり方が変わりつつあるのではないかと感じることがある。
昨年十一月に行われた合同展示会「武蔵美×朝鮮大 突然、目の前がひらけて」では隣り合わせの両校の間に橋が架けられた。展示会の参加者で朝鮮大学校研究院美術専攻の鄭梨愛さんは、五年間続いてきた作品交流で「武蔵美とつながらなくてはという意識がないまま、自然とつながっていた」という。「展示会を準備する対話の過程でも、自分をちょっと離れて見られる機会はあった」と同時に、「自分たちの立場を区切るものが必要だと思った、絶対に」とも語った。そしてそれは橋の上の境界線となった。それは希薄になっていくオリジナリティを受け継がなくてはという意思の表れでもあった。「今現在も加害と被害の現状が続く中で、同じテーブルについて自分は何を発言すればいいかわからないのです、被害の側として」とも語った。それは親しい日本人の何気ない言動に時々うずく心のしこりを連想させた。加害と被害、マジョリティとマイノリティという社会的関係を見ないふりをすればするほど、しこりはますます大きく、痛みは一層激しくなる。この痛みをどうすれば理解してもらえるのか、難しすぎて立ち止まってしまう。「在日朝鮮人」を脱ぎ捨てれば簡単なのかもしれない。でもそういうわけにはいかない。境界線は、マジョリティに引き込まれてしまいそうな不安の表れでもあるのだろうか。
一方、鳥取大学の仲野先生のゼミの学生たち。彼らは朝鮮学校の児童・生徒の作品にまっすぐに向き合い、そこから聞こえる様々な声に耳を傾け、自分の体験を重ね合わせ、新しい何かを発見している。
学美に出会ったある学生は「まだまだ朝鮮学校のことや学美のことは知らないことばかりです。…しかし、知らないことを知ろうとすればするほど、不思議なことにそこには必ず『知らない私』『初めて知る私』が現れるのです」(本誌35号)と。またある学生は「地球市民とか、ボーダーフリーとか、差別撤廃とかいろんなテーマが語られて、どれも素晴らしいと思う、そうなりたいと思うし、そんな社会になってほしいと思う。でも無邪気にそうは思えなくもなった」「今、僕は日本人だと言えるけど、何がどうなって日本人なのかはよくわからない。でも使っていて便利だから使う。でも便利の裏にはちゃんと向き合わないといけないことがある。それに向き合う覚悟ができた。それは学美で出会った人たちの生きざまを見て、感じて、自分との向き合い方、人間との向き合い方自体を考えることができたからだと思う」(37号)と書いている。
加害と被害、マジョリティとマイノリティという社会を、一歩引いて見つめる学生たちの視線に驚かされた。傍観するのではなく、マジョリティの側にいる自分の立ち位置をしっかりと踏まえ、その構図を変えるべく「覚悟ができた」と言える若い世代が育っているのだ。
在日朝鮮人という存在が生まれて百年近く、朝鮮学校ができて七〇年が経つ。その間、在日朝鮮人はいつも日本人と隣り合わせで生活してきた。にもかかわらず無償化問題にヘイトスピーチなど在日朝鮮人への差別、そして何よりもそれらを黙認するかのような世論の冷たさに、私たちはどうしてここまで理解し合えないのだろうかと、在日朝鮮人は消されて行くしかない存在なのだろうかと不安になることがある。
とはいえ私は在日朝鮮人をやめられない。そんな私に今できることは、仲野先生が精魂込めて育てた芽を枯らすことのないよう、厳しい中でも多文化共生を目指す人々の姿をしっかりと書き留めていくことだ。
毎年、山陰地方で展示会を催している日本の人々の間で「学美的」という言葉が使われているという。この「学美的」という言葉を仲野先生は、「人を信じること/人の力を信じること/人を決め付けないこと(年齢、性別、民族、障害の有無など)/自分の力を信じること」と定義されていたという。それは先生の信念でもあるように思う。
一目散にことが進むことはない。迷いながら後ずさりすることもあるけれど、少しずつ着実に理解が深まっていると信じて、先生が育てた芽がどういうふうに育っていくのか、『朝鮮学校のある風景』にその成長を刻んでいかなくてはいけないと心を新たにする。(金淑子・編集部)40
スポンサードリンク