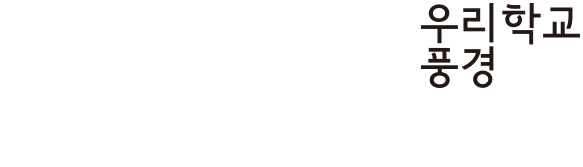特集)凄いぞ!!学美の世界!!(上)
スポンサードリンク
もくじ
連続レポート
日本の大学生が経験した朝鮮学校
全国朝鮮学校美術部合同合宿から、第44回学美中央審査会、そして学美・鳥取展へ
―学美と出会って、わたしと出会った―
- 中村稜子・鳥取大生
- 仲野 誠・鳥取大学教員
1学美と出会う
(仲野 誠)
今回、本誌への寄稿依頼をちょうだいし、筆者(仲野)はどのようなことを書こうか考えた。これまで本誌に寄稿してきたような私の「学美観」を記そうか(たとえば、仲野誠「この時代に在日朝鮮学生美術展と出会うということ」〔本誌23号〕のような内容)、あるいは学美に出会ってきた日本人の感想をもとにしながら学美のリアリティを描こうか(たとえば、仲野誠「日本人来場者によって経験された在日朝鮮学生美術展―その感想から―」〔本誌25号〕のようなスタイル)、迷った。
学美は本年度(2015年度)で第44回を迎えたが、私は37回のときに学美に出会い、それ以来学美から学ばせていただいている。学美を知れば知るほど、一瞬学美の正体がわかったような気がするときがあるものの、実は学美がますますわからなくなり、さらに学美の後をついていってしまう/ついていかざるを得なくなるということを繰り返している。
学美に出会って以来、そのような手探りの展開を続けてきた。本年度に起きた新たな展開は、私の学生(ゼミ生)が、お盆前に淡路島で開催された全国朝鮮学校美術部合同合宿、お盆後に東京の朝鮮大学校で開かれた学美中央審査会、そして全国巡回展のひとつである第44回学美・鳥取展まで、学美の一連の行事にそれぞれに複数の学生たちが参加させていただいたことだった。日本の学生がこれらの一連の行事に参加することは、学美史上初めてのことではないかと思う。
その学生たちのなかに、学美の主要な行事すべてに参加させていただいた者がいる。中村稜子という学生だ。彼女は本年度はじめて学美に出会い、そしてついうっかり一連の行事すべてに吸い寄せられるように参加してしまった。そしてその一連の経験から気づいたことをレポートとして残している。この、「稀有な」中村の論考を紹介することが本稿では意味あることだろうと思い、そうすることにした。
以下、中村のレポートを紹介し、最後に仲野が簡単なコメントを加えることにする。
2.学美と出会って、わたしと出会った
倉吉展実行委員会、淡路島合宿、中央審査会、倉吉展を経験して(中村稜子)
(1)学美を知る
わたしは今から一年ほど前に、日本の小学生が作った美術作品を見る機会があった。その作品は「子どもらしさ」がうかがえるがたがたの丸や線で作られたものが多くあり、わたしは「ああ、子どもらしいな」と子どもたちを可愛く思ったのを覚えている。
それから一カ月後、ゼミで仲野先生から朝鮮学校学生美術展覧会の出雲展についての報告を受け、わたしはとても衝撃を受けた。わたしが一カ月前に見た子ども達の作品と全く異なるものだったからだ。わたしの知る日本の子どもの作品は、テレビで見るキャラクターで溢れており、どれも似たような作品になっていた。それが学美の作品では微塵も感じられず、どの作品も同じ絵がなかった。
「あれ? わたしが感じた『子どもらしさ』って、なんだ?」と思った。わたしは日本の子どもが描かされた作品を見て、勝手に「子どもらしい」としていた。しかし今思えばわたしが一カ月前に見たあの作品には、子どもの自由な表現という意味で「子どもらしさ」はなかった。描かれている線がガタガタしているなどの描かれ方や、作品にキャラクターばかり登場することを子どもらしいと思っていた。そのようなことは子どもらしさではない。
それに反して、学美では子どもの自由な表現が溢れ、飛び出て、とても子どもらしかった。そして、わたしが学美を忘れられないものにしたのが、小学一年生の入学式の作品だった。入学式の入り口から自分に向けて紙ふぶきが迫っている絵だ。華やかな場であるはずの入学式に対して、不安や戸惑いを感じる様子が見て取れた。祝福の紙ふぶきが、自分に向かってあんなに大きく迫ってくる描写は、とても一年生が描いたと思えなかった。しかし、あれはその子が本当に感じた入学式のリアリティだとよくわかる。「これが学美で行われる子どもの表現なのか」と、ぐらっとした。
学美の何が日本の美術と違うのか。どうしてあのような作品が生まれるのか。疑問と困惑が渦巻き、実際に見てみたい、そしてそれを描く子どもたちと先生に出会いたい、そう思った。しかし、それと同時に見てはいけないような、心のどこかにある拒否が、学美から足を遠のかせていた。なぜか踏み出せないわたしがいた。
(2)わたしが学美に踏み出したワケ
わたしが学美と関わることができたのは、今年(2015年)の三月に大学のフィールドワークで訪れたインドネシアで多くの「気づき」を得たおかげだった。全力で人と向き合い、学ぶインドネシアの友人たちに出会い、わたしは「学ぶ楽しさ」、真剣に語れる面白さを知り、そして新しいことに首を突っ込むと驚くことがあることも知った。わたしはわたし自身と向き合い、他者とまっすぐ向き合う力を知ったからこそ、たくさんの人に出会わなければいけないと思ったのだ。そして、重い腰を上げてようやく学美の倉吉展の実行委員会に参加することができた(その時は私は会議後の「飲み会」だけの参加だったのだが)。
はじめての学美の場は、わたしがそれまで知っていた大人たちとは全く異なる人たちだった。彼らはまるで子どものようだった。本気でぶつかり合い、世界平和を求め、発言を恐れなかった。わたしはそこで新しい「大人」を知った。大人とは尊敬されるべき、子どものお手本となるべきものだと思ってきたが、そうではない。大人も「ひとりの人間」であり、大人だって迷い、考え、ぶつかる。その当たり前のことに気づかされた、わたしにとって大きな気づきを得た場が、学美実行委員会の「飲み会」だった。こんな大人たちになりたい――そう思ったわたしは、すでに学美に酔わされていたのかもしれない。
(3)子どもたちへの憧れと壁
学美に酔った勢いで、淡路島で開催された全国朝鮮学校美術部合同合宿に参加させていただく機会をちょうだいした。実際に作品を見ること、そしてその表現者である子どもたちに出会うこと、さらには鳥大の教室のスクリーンの中の人であった先生方にも実際に出会うことができる―とても楽しみにしていた。

淡路島での制作風景(2015・8)
この合宿では、わたしたち鳥大メンバーは外部の人という立場で、子どもたちがどんな風に動き、どんな作品を仕上げていくのかをずっと見ていた。わたしが注目してみていたグループでは、高級学校三年生の女の子が仕切っていたのだが、その女の子はグループ内での会話を大切にし、みんなの作品や思いを引き出せるようにとても努力していたことがわかった。しりとりをしてみたり、笑いを誘ったり、一見作品制作に関係ないように見える行為によって、彼女は彼女なりにチームを柔らかくほぐそうと、あの手この手で努力していた。会話を大切だと知っているからこそできる彼女の様子に、わたしは憧れ、羨ましく思った。そんな子が高校生だなんて、と焦る気持ちがあったからこそ、この合宿では朝鮮学校美術部が羨ましく、わたしもそうであればよかったのにと思った。
しかし、そうなることは決してできない。時を戻せない、ということではなく、今回、常に彼女たちにみえない壁を感じていたからだ。別に冷たくされたという意味ではない。人の背景というのだろうか、その人の後ろにあるものが、わたしが全く理解できない次元にあるということを合宿の間中突きつけられていた。合宿へ来たとき、「朝鮮学校」というレッテルなしに関わっていたつもりだが、飛び交う朝鮮語に戸惑い、背負う世界を互いに共有する子どもたちに、自然で堂々とした静かな壁を建てられていた感覚だった。仲間外れにされた、というような簡単なものではなくて、「ああ、違うのだ」ということを、ずしんと感じさせられた。

淡路島合宿での合評会
そんな彼らは、別に重たい気持ちで過ごしているわけではなかった。むしろ自由でのびのびと過ごしていた。絵を描きに行こう、となってから、なぜか海パンを履いていき、キャンバスは地面に置いたまま丘を転げ回って海で遊びつつ作品を描いた子がいた。「え、それもアリなんだ!」とびっくりした。絵を描くと決めたらそれをやらないといけないと思っていたが、思えば描くタイミングは自由だ。そして描くためにまずその土地を感じてみることが大切だったのだ。彼らにとっては。これに気づいて驚いたとき、どうしても多くの可能性を描けていない自分に対面した。わたしはまだまだ枠から抜け出せていない、と思った。もっと自由に、枠をつくらず、思うまま好きなようにやりたいことを考え、それを実行できる、という環境を持つ彼らを改めて羨ましく感じた。その場を一緒につくっている先生方もすごいと思う。そこは、生きるために必要なことを学び、人間らしさを追求した場だと感じた。だからこそしんどく感じるけれど、わたしはこのしんどさに向き合わないといけないと思ったし、一方で彼らの表現するものに、これからも力をもらいに行かなければ、と思った。
(4)中央審査会で見た「リアルな大人」
淡路島合宿から一週間が経ち、未だしんどさを引きずる中、朝鮮大学校で行われる中央審査会に参加した。この会は、先生たち「大人」の出番だ。子どもたちのために一肌脱ぐための場だった。また、淡路島のときの作品は、短い時間で仕上げたほぼ写生の作品たちだったが、今回出ている作品は授業やクラブでより時間をかけたものだ。見応えのある力強い作品ばかりだった。
中学生から高校生へと審査をしていく中で、ある作品に対して先生方が議論する場面があった。自分の生徒が描いた作品に対して、いかなる考えで制作していたのかを主張するものと、そうだとしても学美的に評価できない、という主張が対立していた。この空気がピリッと緊張している光景に、わたしはハラハラしながらも凄さを感じていた。
わたしが育ってきた環境では、みんな人との争いを避けていた。ケンカはしてはいけないもの。そうなると、どんどんと自分が思ったこと、自分で考えたことが言えなくなり、「正解」を言おうとするようになった。大人や周りの子どもたちを見て、何が今一番求められているかを常に考えていた。だから相槌を打ちながら相手の話や主張を聞くことは得意だったし、相手が言って欲しいだろうことを想像して言うことが多かった。 従順なわたしは、状況に従うというのは当たり前になっていて、疑うことを訓練してこなかったのだ。
学美では、多くの人が自分の意見を持っていた。作品に対して自分の中で咀嚼し、それを表現していたが、自分を取り繕うことに慣れていたわたしには、とても時間がかかる作業だった。「誰かに評価されるようなわたし」の意見ではなくて、「ひとりの人としてのわたし」が考えることを形作り、アウトプットするのはとても難しかった。
さらに、子どもたちの作品の表現について、あそこまで語ることができるくらい、自分の中に訴えがあることがすごいと思った。そうした心の中の譲れないものがあり、対立するのを恐れず、自分がどう思われるかということを恐れずに言い合う大人がいることがすごかった。「大人も必死になるんだ。大人でもひとりひとり考えが違うし、それをぶつけ合うことは悪いことではない。むしろそうしなければおかしいんだ」と気づいた。また、言うことをためらわなくても良いのだ、とも気づかされた。恥ずかしいことはしていないし、わたしが周りからどう思われるかなんて気にするようなことじゃない。しかし、日本社会が空気を読むことを最低限のマナーとしてきたことで、わたしは自分が和を乱し空気を読まないことはとても勇気がいることになっていた。空気を読まなくても受け入れられる、と人と場を信頼していなければできないことだと思う。いや、たとえ人と場を信頼していなくても、違うことは違うと言わなければならないのだ。あえて空気を読まずに心の中の熱いものをぶつけ合う様を、堂々と目の前で見せられ、そんな大人がいることに嬉しくなり、勇気をもらえて、わたしもやってやる、と思えた。実際に先生方のようにできるかどうかはわからない。空気を読まずに生意気になる訓練はこれからだ。

中央審査会(2015・8)
中央審査会に参加して、わたしは先生たちの凄さに圧倒されたが、ある先生が「学美の『汚いところ』も見てほしい」とわたしたちに言った。汚いところがどんなところかはわからないが、わたしたちがキレイなことばかり言うから、そう言ったのだろう。わたしは、先生方のことを聖人君主のようには思っていない。「近づくことのできないすごい人」とは思っていないが、人生の先輩がちゃんと葛藤してるのを見て、すごいと思ったのだ。わたしの知る大人のように、澄ました顔で問題や困難を見ないふりするよりも「リアルな大人の姿」だった。ただ、実際に先生方をまぶしく感じていたのは確かなので、「汚いところもみて」と言われたことで、わたしたち(先生あるいは大人)も君たちと同じところに立っているんだ、と伝えてくれた気がした。同じ人間ですよ、と。先生方を讃えて下から見上げていたわたしたちを、ぐいっと同じ場所へ引き上げてくれた言葉だった。
(5)倉吉展で再会した学美
「リアルな大人」をみた中央審査会から二週間あまり経ち、今度は倉吉で学美が開かれた。これまで、作品の制作現場や審査会に参加させてもらったが、展覧会も初めてだった。
正直に言うと、わたしはこの展覧会に参加して、淡路島合宿や中央審査会のときのような、鋭く突きつけられた感覚はなかった。けれど、今回の倉吉展で学美の力を再確認した気持ちになった。これまで見た学美の総まとめだったと感じる。
これまで感じた学美には、たくさんの力があった。まず、主役である子どもたちの作品には、たくさんの表現があり、楽しみながら遊びながら筆を動かした様子や、苦しさやしんどさを伝えようとするもの、ただ描きたかっただけだろう作品など、様々な考えや感情がのせられていた。中央審査会で見た作品をもう一度考えたり、新しく見る絵に悩んだり、作品を見るのが楽しかった。中にはわたしたちの社会に対する訴えもあり、ヒヤリと感じさせられ、わたし自身考えさせられる作品もあった。このように作品にのせられた自由な感情や表現が、一番の学美の魅力だと思う。
さらに、作品を描く子どもたちに力がなければこのような作品はできないと感じる。淡路島合宿で見たような、自分自身に向き合い、まっすぐ考えて、それを表現することのできる力は本当にすごい。わたしは今まさに向き合う力を身に着けようとしているのだが、その力を作品制作の過程で体験し自分のものにしていた子どもたちがうらやましかった。わたしも考えて表現できるようになりたいと思った。
そして、子どもたちが自由な作品をつくることができるのは、それを支える先生たちがいるからだ。前述の通り、先生たちはわたしの持っていた大人の概念を覆し、自由な生き方を見せてくれたように思う。

鳥取展(2015・9)
このようにして、わたしは再び、作品、子どもたち、先生たちでつくられている学美の力を倉吉展で感じることができた。再び振り返ることができたということが、わたしにとってとても大きかったと思う。学美について知り、吸収してきたが、わたしはこのインプットされたことを表すことができなかったからだ。インプットしたものを、この倉吉展でもう一度作品に出会い、もう一度大人たちに出会ったことで、よりわたしの中で鮮明に色濃く落とし込まれて、こうして今回の感想を書くことができている。たった数回だったが、学美に足を運んだことで、誰とのどのような出会いも、より深く出会うことができたと思った。つまり、まだ数回しか出会えていないわたしは、まだまだ知らない、出会えていないことがたくさんあるはずなのだ。もっとわたしと向き合うために、もっと他者と向き合うために、学美にも、学美以外のところにも、たくさん出かけていきたいと思った。
(6)さいごに
この感想を書いていて思ったことがある。学美に再会して、わたしはわたしと出会うことができた、そう思った。わたしが力だ、と感じた学美の魅力は、わたしが今まで見ていなかったり、見ようとしていなかったり、わたしが気づいていなかったことばかりだ。ひとりではわからなかったわたしのことを、学美のみなさんに出会えたことで気づくことができた。わたしのことをわかるのはわたししかいないけれど、わたしのことを気づかせてくれるのは、わたし以外にしかできないと思う。他者をみることで、学美をみることで、わたしは新しいわたしのことや、新しいわたしの在り方について考えることができ、気づくことができた。さらに、気づいて終わりではなくて、学美と関わるたびにわたしが変わっていくのだろう。ということは、学美にずっと通い続けてもわたしは変わり続けると思う。だからこそ、わたしはわたしと出会うために、もっと外へ出なければいけない。
今回の倉吉展のみならず、実行委員会から、淡路島合宿、中央審査会まで、皆さんの大切な機会にわたしたちが関われたことに、本当に感謝している。わたしたちの言葉を「ひとりの人」として聞き、真剣に応えてくれて、そして、特別扱いしないでくれて、とてもありがたかった。みなさん、これからもよろしくお願いします。
3.自分の生き方と学美(仲野)
以上、一学生のレポートを全文紹介した。このレポートを読み、筆者(仲野)自身がはじめて学美に出会った日のことを思い出した。それは二〇〇九年八月に朝鮮大学校で開催された第37回在日朝鮮学生美術展の中央審査会の会場だった。その会場で私が率直に思ったのは「この時代にこんな先生方が存在していたのか」ということだった。審査会で子どもたちの作品群、そしてそれを取り囲む先生方の様子をみて、筆者はただ率直に驚いた。私の目の前の美術集団は、子どもたちの力に徹底的に信を置き、自分自身が大きく揺れながら仲間たちと真剣に議論を交わして枠をはみ出している子どもたちの作品群にまっすぐに向き合う先生方だった。子どもたちはその愛に包まれながら安心して自由奔放に既成の様々な枠からはみ出て自己表現していることを筆者は直感し、驚愕した。
文字にしてみれば、このようなことは教育者としてごくあたりまえの行為のようにも読めるかもしれない。しかし、このごく「あたりまえ」の行為が理想論として片付けられてしまうような、あるいは現実味を感じられない行為としてしかみなされないような危機的な状況を私たちはいま生きているということを中村レポートは物語っているのではないか。このレポートが描いている学美は、換言すれば「私たちがやらせてもらえなかったこと」をしているかのように読める。さらには、「そのようなことをしていいのだということにすら気づかせてもらえなかったこと」を目の前の生徒たちは軽々とやってのけているという事実に対する驚愕なのかもしれない。

鳥取展(2015・9)
学美は「私たちがなれなかったもうひとりの自分」のように思える。同時にそれは「私たちがこれからなれるかもしれないもうひとりの自分」なのだろう。すなわち学美はこの時代を生きる私たちの可能性でもあり、未来でもある。そのようなことを考えると、この時代に学美と出会うということは、学美の力を自らの中に織り込むことだと思える。それは私がこれまで気づかなかった自らの可能性と出会い、自分自身に出会いなおす機会を与えてもらうということではないか。
中村が言う「学美と出会って、わたしと出会った」ということは、まさに他者と出会うことによって生まれるそのような可能性のこと―すなわち学美の可能性を自らの可能性に転化すること、学美の可能性を自らのうちに織り込むこと―のように思える。学美とはもちろん朝鮮学校の生徒たちの美術作品群のことである。それが学美のすべてだ。しかしその作品群は同時にこの時代を生きる私たちの生き方の可能性そのもののようにも見える。
そもそも、他者に出会うことが自分自身に出会いなおすということにつながるということに気づいたこと、それ自体が学美から得た糧なのかもしれない。学美との出会いがなければ、他者との出会いが自分自身を見つめることにつながるということにすら私たちは気づかないままだったのかもしれない。34